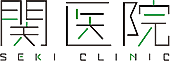2025立冬(りっとう)/こよみと健康その43
2025.11.07 こよみと健康
立冬(りっとう)
(2025.11.07~2025.11.21)
空気や風に冷たさを感じる季節になりました。地域によってはすでに初雪が観測されているところもあるようです。
【季節の養生】
ついに暦の上では冬の始まりとなりました。冬の養生のポイントは何といっても「寒さ」対策そしてエネルギーを蓄え、体力作りにも適した時期でもあります。空気の乾燥も強まるのでインフルエンザなどの感染症や肌の乾燥対策も大切ですね。
「寒さ」は中医学で「寒邪」と言われ、気血の巡りを悪くし、肩こりや生理痛、腰痛や関節痛、しもやけなどの痛みの原因になったり、胃腸の動きを鈍くしたりするなどの影響を及ぼすと言われています。
まずは前回も挙げた三首(首、足首、手首)を守るマフラーやレッグウォーマー、靴下、手袋また腹巻などを活用して体を冷やさないようにしましょう。適度な筋肉トレーニングや、ストレッチ、入浴などは体の中の気血の巡りを良くするのでお勧めです。日中の日光を浴びるのを意識した散歩なども良いですね。
また、おでんや鍋なども美味しい季節になりました。鍋は生姜やねぎ、白菜や大根など野菜やきのこをたっぷりとれるのも嬉しいポイントです。今後の寒さや年末年始の忙しさに備えてぜひ体力をつけていきましょう。
【生薬と漢方その19】
漢方薬は色々な生薬を組み合わせてつくられています。実は身近にあるものも多い生薬に焦点をあててご紹介していきます。
「地黄(じおう)」
性・味:微温・甘 帰経:心肝腎
代表的な漢方薬:八味地黄丸 四物湯
地黄はゴマノハグサ科のアカヤジオウの根を日干ししたもの(乾地黄/生地黄)または蒸して乾燥したもの(熟地黄)です。
「養血の要薬」とも呼ばれ、四物湯の構成生薬の1つとして貧血やめまいなどに使う漢方薬に使うほか、腰の痛みや体力低下に対しての滋養強壮作用がある補腎薬に使われています。
ちなみに中医学では熟地黄と生地黄で使い分けられており、熟地黄が補血薬という分類に対して生地黄は清熱涼血薬となり性・味は寒・甘苦と、清熱作用と陰を補う作用が強いとされています。
体質によっては胃もたれや軟便などの消化器症状が出ることがあるので少し注意が必要ですが、薬局で滋養強壮という言葉とともによく見かける八味地黄丸の名前にも入っており、日本でかなり親しまれてきた生薬の1つです。
【季節のできごと】
七五三(しちごさん)
七五三は子供の成長を祝う伝統行事です。3歳、5歳、7歳の節目に健康と成長を願い3歳は髪置きの儀で男女ともに、5歳では袴着の儀で男の子、7歳では帯解きの儀で女の子が対象となります。もともとは旧暦の11月15日に行われており、現代では新暦の11月15日前後や家族がそろう土日にお参りやお祝いを行う家庭が多いです。この時期に神社などを訪れると着物や袴などの晴れ着姿の子どもを見かけますね。七五三といえば千歳飴(ちとせあめ)もおなじみで赤と白の細長い飴で、粘り強く細く長く子供の長寿への願いが込められています。寿や松竹梅、鶴などの縁起の良いイラストが描かれた細長い袋はこの時期ならではの風物詩の1つです。
【お知らせ】
いつもこよみと健康を読んでいただきありがとうございます。このたび担当者が出産のため漢方外来とともにこちらの更新も少しお休みさせていただくことになりました。
また落ち着いたら再開させていただく予定です。今後ともよろしくお願いいたします。
(薬剤師・国際中医専門員 國兼)