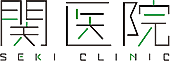2025立夏(りっか)/こよみと健康その31
2025.05.05 こよみと健康
2025立夏(りっか)(2025.5.5~2025.5.20)
暦では夏の始まり、「陽」のエネルギーに満ち始める季節です。
【季節の養生】
気持ちのいいお出かけ日和の日が増えるとともに、紫外線や日差しが気になる時期になりました。適度な日光は体内時計を整え、漢方では「陽」のエネルギーをチャージできると考えられているためとても大切なのですが、日焼けやシミなど肌の負担はどうしても気になってしまいます。帽子、日傘、サングラス、パーカーやアームカバーなどせっかくなのでお気に入りのものを見つけて対策したいですね。また状況に合わせてこまめに日焼け止めを活用するのも大切です。
また、紫外線は活性酸素を増加させ肌の酸化を引き起こし、シミやシワなどの原因になると言われており、「抗酸化作用」がある「ビタミンA・C・E」などを含む食べ物を摂ることも対策になります。前回挙げたイチゴのほか、メキシコ産であれば4月~6月が旬となるアボカド、春キャベツ、トマト、またキウイフルーツやバナナなど様々な食材をぜひ楽しんで対策していきましょう。
【生薬と漢方その7】
漢方薬は色々な生薬を組み合わせてつくられています。これから実は身近にあるものも多い生薬に焦点をあててご紹介していきます。
「桂枝(けいし)」
性・味:温・辛甘 帰経:肺・心・脾・肝・腎・膀胱
代表的な漢方薬:桂枝湯 葛根湯 安中散
桂枝はクスノキ科の若枝、またはその樹皮を指し、香りが特徴的な生薬です。日本ではほぼ同等に扱われていることが多いのですが、桂皮(けいひ)/肉桂(にっけい)という生薬はクスノキ科ケイの幹皮を使っており、より温める作用が強いと言われています。
スパイスの王様と言われるシナモン、日本でもニッキという呼び名で薬だけでなく、シナモンロールやアップルパイ、チャイや八つ橋など色々な食べ物にも活用され、世界中で親しまれていますね。ちなみにシナモンは紀元前4000年ごろからエジプトでミイラの防腐剤として使われており、世界最古のスパイスの1つとされています。
漢方薬としては頭痛などの症状や特に風邪のひきはじめに使用する葛根湯や、胃腸が冷えて不調の時に使用する安中散などに活用されている生薬です。
【季節の楽しみ】
5月5日
5月5日はなんといってもこどもの日、端午の節句として有名なのですが、「薬の日」でもあることをご存知でしょうか?実は「日本書紀」に約1400年前、推古天皇が5月5日(旧暦)に薬草を採集する「薬狩り」を行い、それ以降毎年の恒例行事となり「薬日(くすりび)」と呼ぶようになったという記載があるそうです。菖蒲(しょうぶ)やよもぎなど香りの強い、邪気を払うとされる植物などを採集し、今でも親しまれている菖蒲湯のほか、沈香(じんこう)、丁子(ちょうじ)などを入れて「薬玉(くすだま)」をつくり、軒先にかけて無病息災を願ったとのこと。菖蒲湯やお香などですっきりした香りを楽しむのもよさそうですね。
(薬剤師・国際中医専門員 國兼)